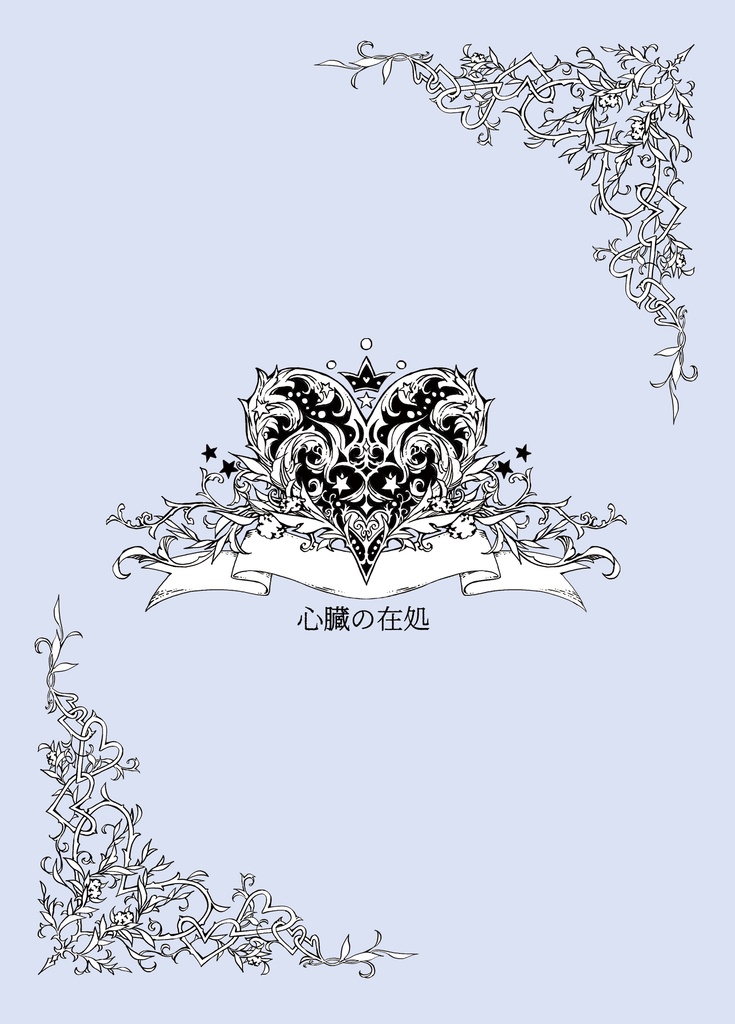心臓の在処
- 物販商品(自宅から発送)あんしんBOOTHパックで配送予定支払いから発送までの日数:10日以内在庫なし¥ 200
A6/28p(2022年12月発行) アーサーとの出会いと別れの中で、己の心臓の在処を知るオズの話。 【サンプル】 「ここにあるんだよ」 自分のものではない血を指先から滴らせたフィガロがそう言った。ここ、と言われたあたりを見つめて、オズはなるほどと思う。 そこには、既に動きを止めた誰かの心臓があった。フィガロがわざわざ死んだ人間の身体を切り開いたのは、オズにこれを見せたかったからであるらしい。石のように食べることもできない死体を拾ってきたのには理由があったようだ。 心臓は魔法使いにとっても弱点となりうる、とオズに教えたのはフィガロだ。基本的に、魔法使いの肉体は人間のそれと同じ構造をしている。それ故、弱い部分もまた似ていた。 無論、心臓を一突きされたところで、力のある魔法使いならば生き延びる術もあるだろう。ただ、心臓が血液を全身へ巡らせる器官であることを考えれば、そこを狙った攻撃は間違いなく警戒すべきものだ。 魔法使いは自身の身体の一欠片さえも他者に渡してはならないとされている。オズやフィガロのような強い魔法使いならばなおさらだ。髪の毛の一本も、血の一滴も、自身の支配下に置かなくてはならない以上、血液の集中する心臓は確かに重要な存在だと言える。 「おまえにとっては、わざわざ意識して守るものじゃないかもしれないけど」 フィガロはそう前置きして、オズに心臓の話をした。何をすれば生き物は死ぬのか、生きるためには体のどこを残せばいいのか。それはオズにとって、本能的に理解していたことだ。ただ、フィガロはその理解を知識と思考を介したものにしたいらしい。いずれきっと役に立つことがあるはずだから、と。 一体何の役に立つのか、オズにはわからない。けれど、物事の仕組みを知ることは決して嫌いではなかった。世界を紐解けば、それはオズ自身を理解するということにも繋がる。双子に捕まるまで、自分自身や世界のことを〝そういうもの〟として漠然と受け入れていたオズにとって、新鮮なものがそこにはあった。 「おまえも、同じ場所にあるのか」 オズが訊ねると、フィガロは「多分ね」と苦笑を浮かべ、手に付いた血を拭き取りながら答えた。そして、目線を合わせるように屈むと、オズの腕を掴んで手のひらに自身の左胸を押し付けてくる。 ドクンドクンと、血液を全身に行き渡らせるための動きが手のひら越しに伝わってきて、オズはなんとなくぞわぞわするものを感じた。生きている──そんな当たり前の実感も、オズにはあまり縁のないものだったと言っていい。 オズが誰かの死を強く認識するのときがあるとすれば、それは相手の生温かい血飛沫を浴びた瞬間くらいかもしれない。オズの周りは、圧倒的に死の方が多いのだ。 目の前のフィガロが生きていることは当然わかっていたし、正しく認識しているつもりでいた。けれど、改めてそれを自身の肌で感じるのは落ち着かないものがある。オズにとって、生きているということは、石になっていない状態であるという意味しか持っていなかったのだから。 「わかった?」 「…………わからない」 「あはは、わからなかったかぁ」 「……ただ、おまえが生きていることはわかった」 どこか楽しそうに訊ねてきたフィガロに、オズは素直な感想を漏らした。正確に彼の心臓の位置がわかるわけではなかったが、彼の心臓が正常に機能していて、それが彼を生かしているという事実はわかったような気がした。そして、そこを狙って攻撃すれば、フィガロもあっさり石になるのかもしれないということも。 フィガロはオズのそんな言葉をどう受け取ったのか、一瞬目を見開いてからふっと微笑む。彼の柔らかい眼差しに言いようのないくすぐったさを感じて、オズは顔をしかめた。凪いだ海のようなオズの心に、フィガロは時折僅かの波紋を生み出すことがある。オズはあまりそれが好きではない。 ただ、なんとなく拒みにくいと感じている自分がいることは、薄々自覚していた。スノウとホワイトとフィガロは、オズの世界に入り込んできた初めての他者だ。そして、それは彼らが最後になるだろうといい気もしている。 だからなのだろうか。オズは彼らとの触れ合いを拒みはするが、激しく拒むことはあまりなくなってきていて。 「あはは、なんだそれ」 笑いながら頭を撫でてこようとするフィガロの手を、オズは拒むように弾く。けれど、フィガロは少しも気分を害した様子は見せず、代わりにオズの左胸のあたりに手を伸ばしてきた。直感的に、オズはそこに自身の心臓があるのだと理解して、ぴたりと動きを止める。 「おまえの心臓はこのあたりかな。おまえもちゃんと、生きてるよ」 *** とくんとくんと弱々しい音を刻むアーサーの左胸に耳を当てながら、オズはゆっくりと息を吐いた。生きている──それだけでこんなにもほっとするとは思ってもみなかったと言っていい。元より、石にして食べるつもりで拾った子供だ。その生死に自分がこうも振り回され、動転することになるとは、オズ自身信じられないことだった。 「アーサー……」 けれど、そのあまりにも弱い心音にざわめく自分の心は偽れない。いずれは、強い魔法使いになるであろう原石だ。だが、今はまだか弱い少年。弱き者は些細なことでいとも容易く死を迎えると、知らぬオズではない。目の前にある命は、オズが思っている以上に脆く脆弱なのだ。 オズはふと、アーサーを拾ったばかりの頃のことを思い出した。当時のオズは、幼い魔法使いが生きるのに何が必要かわかっていなかった。 それに、アーサーを生かそうという意思も今ほど強くはなかった。もしもフィガロの介入がなければ、今頃アーサーは石になっていたかもしれない。 それが今は、アーサーの身の安全のため周囲の危険は徹底的に排除し、好奇心旺盛な彼に危険が迫っているのを察知すればなりふり構わずすっ飛んで行くのだから、変化とは恐ろしいものだ。アーサーが無茶をして死にかけたときに、「死ぬのか」と問いかけた冷静なオズは、どこかへ行ってしまっていた。 オズは自身に訪れたその変化の正体を知らない。だが、不思議と今の自分に違和感を覚えてはいなかった。いずれこうなる運命だった──そんな思いがあるからか。 アーサーは、オズの世界に入り込んできた四人目だ。そして、今度こそ彼が最後になるであろうという確信がオズの中にはある。二千年生きてようやっと、オズの世界は完成したのだと。 だからこそ、それを欠けさせたくないと切に思うのかもしれない。アーサーを失いたくないと。 「ここに、あるのか」 オズはアーサーから身を離すと、改めて彼の左胸に手を置いた。きっと、アーサーの心臓はオズの手のひらよりも小さいだろう。今オズが魔法を放てば、簡単に握り潰せるものなのだ。 それが、オズの守らなくてはいけないものだった。 アーサーを誰にも奪われたくなければ、石にして食べてしまえばいい。だが、この心臓が止まってしまえば意味がないのだと、オズは薄々わかり始めている。そんなものは、自分の望みではないと。 だから、オズが守らなくてはならないのだ。